1) 研修
◆はじめに、「あいあい」さんの活動内容をご紹介いただき、引続き「児童発達支援」とは何か? 「放課後等デイサービス」「療育(発達支援)」とは?とレジュメによる講話となった。
◆保護者支援について
児童発達支援は診断名がついてなくても利用できるが、様々な悩みを抱えた保護者が利用している。
保護者支援というのは、難しいものが多い。(・誰に話せばいいかわからない ・検索すればするほど我が子が発達障がいの特徴に当てはまる ・どの情報が我が子に会うのかわからない等々)
◆保護者の気持ち…大きく分けて2つ
①私の子が発達障害のはずがない。
②発達障害なら この子が将来自立できるようにしないといけない。
割合としては、①が多い。
①の方々には、子育てサポートまたは習い事の感覚で利用されるといいのではと伝える。利用する中で保護者が気持ちを受け入れていく可能性もあるので、信頼関係の構築を優先している。発達支援では、お母さん方が自分の気持ちを整理するところでもある。タイミングを見て、「〇〇の傾向が強いので受診された方がよいかもしれません」と伝えている。
②の方はお子さんが困り感を持っていることで前向きに考える方が該当している。支援の質(内容や要望)のこだわりも強い方が多いので、丁寧な説明を心がけている。その支援の目的や意図、効果を具体的に説明し納得いくよう話している。
◆保護者支援の支援方法・・・「ペアレント・トレーニング」
発達障害向けの方法ではあるが、考え方等は子育ての中でも使えるので、ぜひ詳細を学んでほしい。行
政(熊本市)で研修も行っている。(*内容はレジュメ参照)
2)交流会
お茶をいただきながら、質疑応答の時間とした。参加者より多くの質問があり、具体的な支援方法などを学ぶことができた。
◆質問① トイレトレーニング(排便)を保育園で失敗して、行けないで悩んでいる保護者がいるが、どうしたらよいか?
ANS.・「トイレに行きたいカード」を作り、先生に渡すようにする。
・トイレに行きたい子と一緒に行かせるよう先生にお願いする。
・お家で、まず出来るようにする。
◆質問② 言葉がでない。
ANS. ・忙しいとスマホを持たせてしまう方も多い。またコロナ禍マスク着用で口が見えないことも影響している。ゆっくりしゃべる。コミュニケーションを取る。
◆質問③ 見知らぬ人へも抱きついたりする。母親は子育てにいっぱいいっぱいで、その子を突き離すように見られる。小3。抱きついてくる許容範囲は何歳まで?
ANS. ・幼児くらいまで。・母親の子育てに余裕を持たせることが大事。子どもが満たされるスキンシップを日常に入れられる余裕。母親と一緒にスケジュールを立てる。(支援)
・小学3年生が発達改善のピーク。それ以上になると、改善ではなく自分の特性とどう向き合っていくかということになる。
・今の子育ては、大人も他の人に助けを求められるようにならないといけない。
どういうところで相談できる、という情報発信をすることが大事。
・親にも課題がある。余裕・時間がない。コミュニケーション欠如。人に言いたがらない。弱みを見せられない。人と関わりたがらない。
|
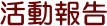 一覧に戻る。
一覧に戻る。
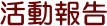 一覧に戻る。
一覧に戻る。